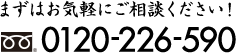 営業時間 9:00~19:00(年中無休)
営業時間 9:00~19:00(年中無休)
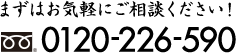 営業時間 9:00~19:00(年中無休)
営業時間 9:00~19:00(年中無休)

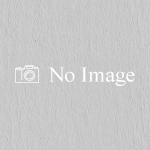
川島甚兵衛(2代目)京都西陣の織芸家、織物業者
ヨーロッパ視察をきっかけに、織物による室内装飾を考案。古き良き織りの伝統をもとにしつつ歴史に先駆ける精神で日本のテキスタイルを研究し、生涯をかけて織物技術の進歩と発展に尽力して、日本の美術織物製作の基礎を築きました。
川島織物の創始者・初代川島甚兵衛の長男として1853年、京都に生まれた2代目甚兵衛(本名辨次郎)は、今日も続く繊維会社・川島織物セルコンの礎を初代とともに築きました。
晩年には帝室技芸員にも選任され、織芸家としての頂点を極めた2代目甚兵衛(以降甚兵衛)は生前、事あるごとに「自分が今日この織物を創作し得られたのは、みな父の教えによるもの」と語っています。
生涯を織物に情熱を傾け続けた甚兵衛の原点のひとつとなったのが幼い頃に行った父との巡回の旅です。父は甚兵衛を連れ、越前、加賀、越中の織物業者をたずねる旅に出ては、目で見て実際に確かめ、手に触れてその感触を知る大切さを教えこみました。
織芸家としての起点になったともいえる幼少期に重ねたこの旅の経験は、父のうんちくをかたむけた詳細な説明と共に甚兵衛の脳裏に深く刻みつけられ、織物の持つ高貴さと緻密な品格、そして織りの技術と伝統の調和を考えるうえで、その後の織芸家としての甚兵衛の人生に大いに影響したことは言うまでもありません。
初代が病死し、甚兵衛が家名を継承したのは1879年のこと。
折しも、当時の西陣は明治維新により、将軍をはじめとする武家という顧客を失い、さらには東京遷都の影響により、時代の翻弄による消沈は、目に余るほどでした。そのような情況にもかかわらず、甚兵衛は新時代にふさわしい近代化への道を着実に歩んで行きます。
日本国を豊かにし、伝統工芸である西陣織を継承していくには、諸外国との交流を除いて他にないと考えた甚兵衛は、丹後ちりめんに西陣織の技法を応用した製法を開発して国内外に技術を伝えたのを筆頭に、世界に目を向けた発展を重視して積極的に推進します。
1886年にはヨーロッパ視察の命を受け、ドイツ、フランス、イタリアなどの織物技術を視察しました。そこで甚兵衛は、今では総称してタペストリーと呼ばれる、フランスのゴブラン織が日本の綴織(つづれおり)に匹敵する原理だということを知り、帰国後は綴織機の改良を熱心に重ね、より精緻で芸術性の高い作品作りを志します。
さらに、1888年には明治宮殿の室内装飾に国内で初めて織物を用いて、インテリアファブリックの歴史をスタートさせるとともに、宮内省織物御用達の公許を得ました。また、諸外国の万国博覧会でさまざまな賞を受賞して作品が宮内省に買い上げられると、それらの作品は海を渡ってロシア皇室やアメリカ大統領に贈られるまでに珍重され、甚兵衛の技術は世界的に高く評価されました。
ついには、甚兵衛は日本の織物を芸術の域まで高めることに成功し、織文化における多大な功績を確かなものにすると、明治政府より帝室技芸員に任命されます。
また、甚兵衛は58歳でこの世を去るまで、実に世界中から染織品およそ8万点、古書約2万点を蒐集し、織物文化の継承にも惜しみなく私財を投じたと記されています。
こうして甚兵衛が残した業績と英知、また織物に対する信条は、3代目、4代目川島甚兵衛へと受け継がれ、今日に伝わる織の文化に脈々と息づいています。
1853年 京都に生まれる
1859年 平井義直に学問を学ぶ傍ら、父である初代・甚兵衛としばしば織物業の巡回の旅に出て各地の織物に触れる
1879年 初代没後、家名を継承する
1881年 丹後ちりめんに関する建白書を京都知事に提出。技術を駆使して独自の製法を開発した結果、新たに川島式ちりめん機を国内外に伝授する
1884年 初代の遺志でもあった西陣織物工場を建築
1886年 海外視察の命を受け、欧州の織物業を視察する
1887年 帰国後は、より精緻な綴織を目指し実用的な織り機の研究を重ねる
1891年 宮内省より織物御用達の官許を受ける
1892年 緑綬褒章受章
1898年 帝室技芸員に選出される
1902年 勲六等瑞宝章受章
1910年 京都の自宅にて死去
●犬追物の図(1890年)
第3回内国勧業博覧会出品。宮内庁買上げ。後にロマノフ家に贈られる
●葵祭の図(1893年)
宮内庁買上げ。後にアメリカ大統領に贈られる
●慈母観音図(1895年)
第4回内国勧業博覧会出品作品。宮内庁買上げ。現在は東京国立博物館蔵
●群犬の図(1900年)
武具曝涼図とともにパリ万国博覧会に出品された
●百花百鳥之図(1905年)
「百花百鳥之間」を装飾するために制作され、ベルギー開催の万国博覧会に出品された作品