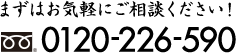 営業時間 9:00~19:00(年中無休)
営業時間 9:00~19:00(年中無休)
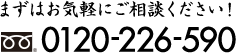 営業時間 9:00~19:00(年中無休)
営業時間 9:00~19:00(年中無休)



隠元禅師を支持した黄檗宗の僧が日本に持ち込んだ大陸の新しい文化は、いわの美術も査定と買取を行っている煎茶道具や書の掛け軸、画賛の軸、器物を日本にもたらしました。
黄檗宗萬福寺は開山の隠元禅師が煎茶を始めたことから煎茶道、売茶(茶を定価を定めずに売り、煎茶と共に禅宗の教えを説法する)、売茶を行った売茶翁の高遊外と非常に縁が深く、売茶堂という建物も遺っています。
医術や、食生活においてもたけのこなどの野菜類の輸入、「普茶料理」という油脂とタンパク質をしっかり取り入れた中国風の精進料理に至るまでその影響は多方面に渡りました。鎖国体制の下で海外との交渉が中国、オランダ、朝鮮に限定され、異国の文化の窓口が長崎の一都市のみに限定されるなか、黄檗山萬福寺は中国文化を伝える拠点となり、江戸当時の最先端の中国に関する情報発信の基地ともなりました。

黄檗宗の「唐様の書」は一番の特徴であり、広額・聯・寿章、詩偈などの形で示された書法や、中国明代の気風を受けた明るくのびやかな書風が一世を風靡し、中国僧・日本僧を問わず、黄檗僧の間に永らく受け継がれてきました。
古来の日本では、中国の伝統書風から離れた禅僧の書が「墨蹟」として珍重されてきた経緯があります。
中でも
の 隠木即による書は「黄檗の三筆」として特に珍重されるものとなっています。
黄檗宗は日本の画家にも大きな影響を与えました。
池大雅は七歳の時に十二代住持・杲堂元昶の前で大字を書き、直々に「神童」と称され、それ以降、柴山元昭(売茶翁)や悟心元明らと交遊を続けました。黄檗画僧の海眼浄光(鶴亭)は木村兼葭堂(きむらけんかどう)や葛蛇石(かつだせき)などの弟子を育て、伊藤若冲の画風形成にも大きな影響を与えました。